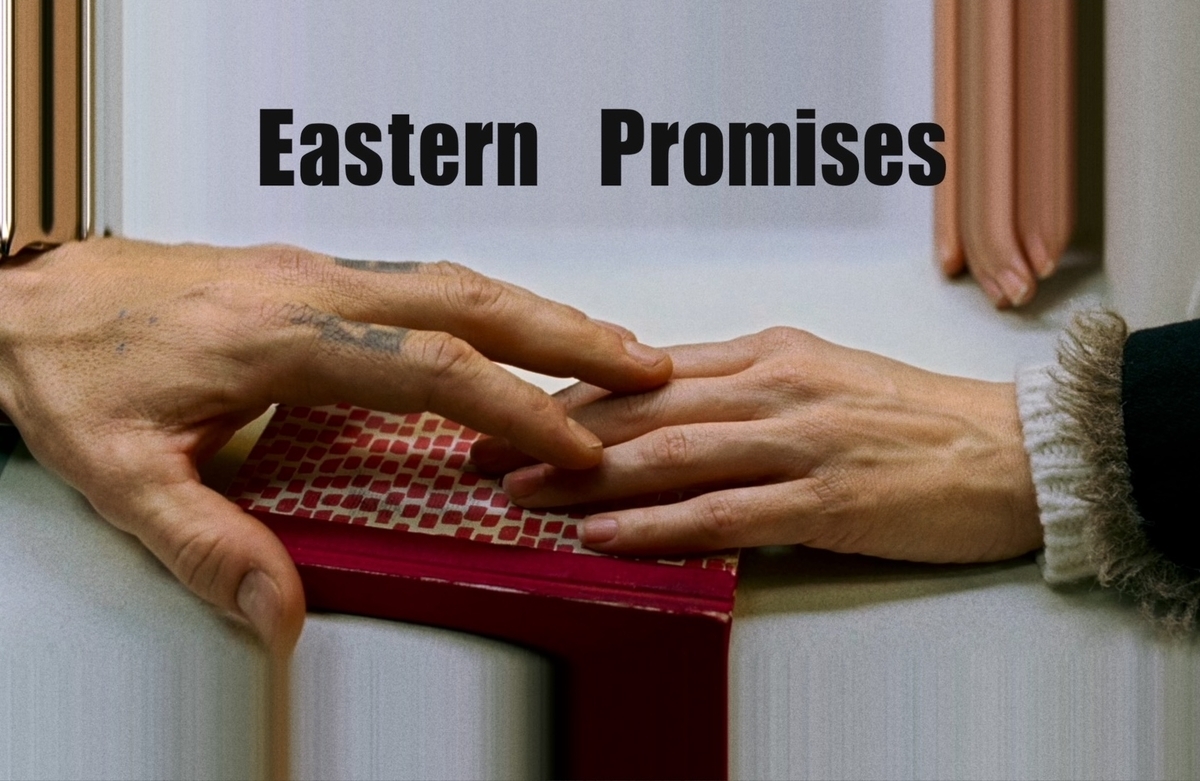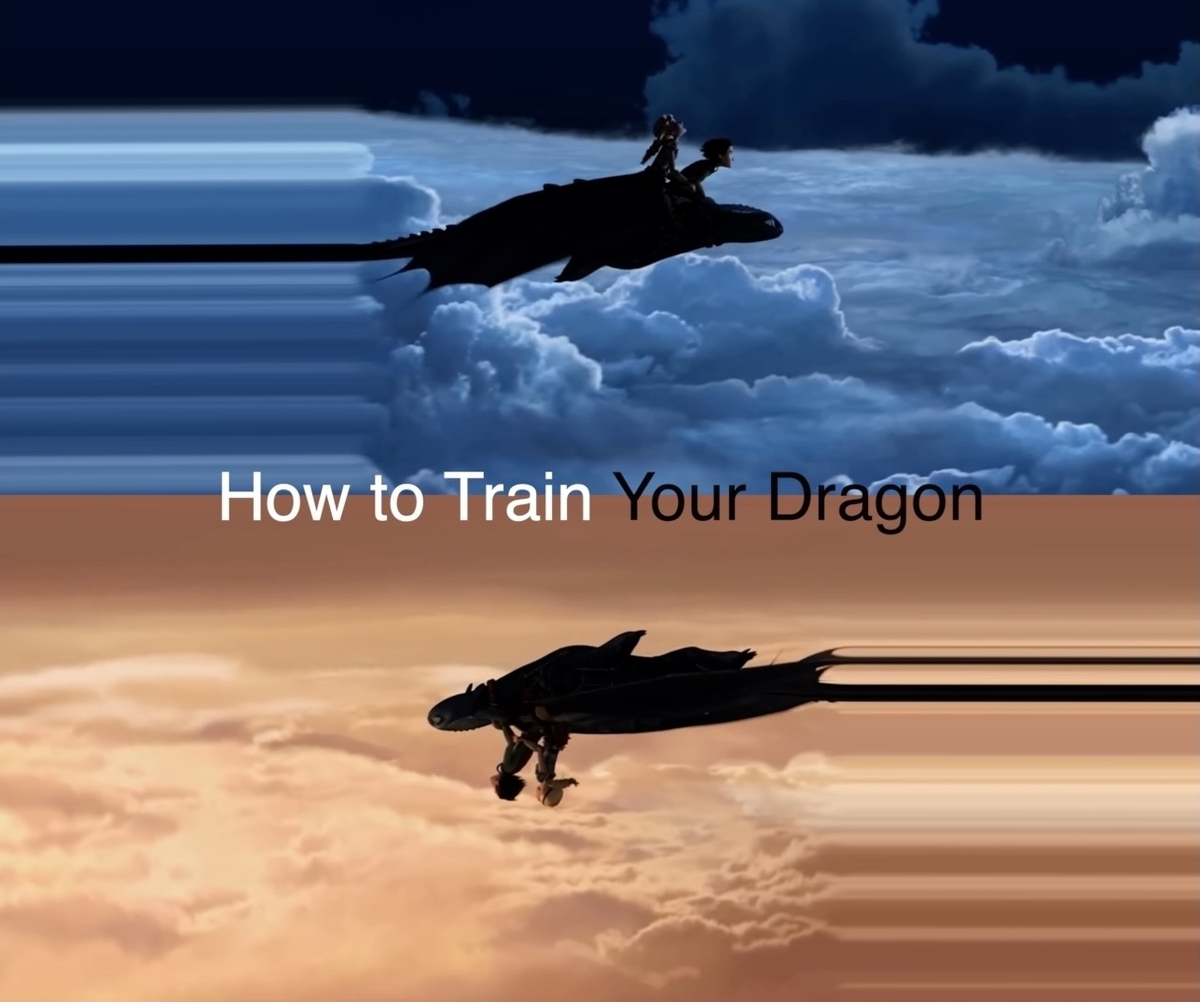『劇映画 沖縄』
原題:劇映画 沖縄
監督:武田敦
脚本:武田敦
撮影:瀬川浩
出演:地井武男、佐々木愛、加藤嘉、中村翫右衛門、飯田蝶子
〈第一部:一坪たりともわたすまい〉
昭和三十年代、「ウチナンチューの物を盗れば泥棒だが、アメリカーの物を盗るのは戦果だ」という信念のもと「戦果アギヤー」として米軍物資盗みをしていた主人公の三郎は、暗闇の中で米軍による平川村の土地強奪を目撃してしまう。当時、沖縄では米軍による土地の強制接収が行われており、生活の全てを奪われ農民たちは苦しんでいた。そんな中、接収された一族の土地に侵入し、畑仕事を再開した老女が米軍戦闘機の銃撃により殺されるという事件が起こる。我慢の限界を超えた三郎と農民たちは抗議のための行進を決意する。
〈第二部:怒りの島〉
十年後、軍基地労働者として基地内で働いていた三郎は組合活動に目覚めていく。米軍政下での弾圧や日米地位協定により理不尽な状況にあった沖縄。ベトナム戦争長期化に伴い苛烈になっていく基地内労働に苦しむ日々の中、三郎は労働組合を通して、権利獲得と復帰運動のための戦いに進んでいく。
戦後、沖縄の歴史は「闘争と分断の歴史」と形容することができる。
沖縄の戦後史は「本土復帰」を一つの着地点に定め、県民“一致団結”の物語として語られる場合が多い。しかし、実際にはそうではない。植民地支配に積極的に加担し支配者と同化しようとする者、日和見的に傍観してしまう者、疲れ切って諦めてしまう者、それらを糾弾し最後まで必死に抵抗する者、沖縄のアイデンティティを平和主義に見出す者、それを資本主義に見出す者、様々な想いや政治的せめぎ合いの中、闘争と分断を繰り返すことで今日の沖縄は形作られてきた(そのため、戦後沖縄の物語は必然的に“民主主義についての物語”にもなっていく)。
本作は、現在の主流になっている「単純化された戦後の語られ方」からでは見過ごされがちな「一枚岩だったわけではない沖縄」と、その中で生き抜こうとする人々の戦いの日々を垣間見ることができる。
本作が公開された年が1970年というのも特筆すべき点だ。
“戦後の語られ方”が単純化されて来たように、“戦中の語られ方”も現在に至るまでにある特徴的な変化がある。それは「誰の視点でどのような思惑のもと語られるのか」というイデオロギー的な変化だ。現在一般的になっているのは「戦争被害の壮絶な体験」や「反戦と平和の尊さ」を訴えるような、いわゆる「市民の視点」からの語りだが、これが形になり出したのは1970年代以降のことであり、それ以前の沖縄戦における戦争体験は「軍国主義的な視点」に則った殉国美談のものが主流だったとされている(そしてそれは観光産業の一部として利用されている)。
時代を反映した末に本作が生まれたのか、または共鳴し合い同時多発的に発生した現象なのか(その可能性は限りなく低いと思うが)、リアルタイムで体験した訳ではない平成生まれの自分には判断しかねるが、本作が1970年という一つの時代の境目に公開されたことには大きな意味がある。
もう一つ本作で重要なのが地理的な意味での沖縄の「圧縮」と、起こる出来事の時間軸の「整理」が行われていることだ。本作は戦後県内各地で実際に起こった“植民地支配下が故の暴力”を中心に物語が展開するが、それらが起こる場所はある程度の改変がなされている。登場人物が口にする地名や実際に画面に映る場所、土地ごとの位置関係にも若干の飛躍があり、明らかに「地理的な圧縮」が行われている。また、起こる出来事の時期には史実と若干のズレがあり「時間的な整理」がなされている。それらが及ぼす本作への影響・効果は後述するが、実際の出来事を採用しながらも、無数のそれらを地理的・時間的に束ね、一本の筋道を持つ物語にする本作は、沖縄という土地を文字通り“劇映画”化していると言える(タイトルはその宣言だともとれる)。
様々な要素と映画演出が絡まり合う本作は非常に多層的だが、その中心にあるのは「アイデンティティを巡る物語」だ。もしくは「主体形成に関する物語」と言えるかもしれない。戦後から現在に至るまで、国際戦略の中でのみ存在価値を認められ、それを内面化するにまで至った沖縄(書いてて悔しくなるが)。常に客体化され続けた「太平洋の要石」の中で、それでも主体的に「生きていくこと」を掴み取ろうとした当時の県民と沖縄。それこそが本作のテーマだ。
鑑賞後、強く感じたのは「今の視点で本作(または当時の沖縄)をどのように語れるか」または「どのように語り繋いでいくべきなのか」ということだった。本作公開当時の県民達も、そして本作の中で生きる人達も、今の沖縄を作り上げるために全力で闘い、未来へと平和を繋いだ先人達だ。その後に生まれ、訪れた平和を享受しているだけの自分としては感謝してもしきれない(たとえそれが仮初の平和だとしてもだ)。しかし、戦後沖縄には彼らよりもさらに周縁へと追い込まれた人たちがいたのも確かであり、そんな彼らを本作や自分を含めた沖縄県民、または沖縄の戦後史が見過ごし、差別的な扱いをして来たのも事実だ(そういった戦後沖縄で見過ごされた権力勾配を「ポストコロニアル・フェミニズム」の視点から捉え、さらに先へと問い直したのが玉城福子著の「沖縄とセクシュアリティの社会学〜ポストコロニアル・フェミニズムから問い直す沖縄戦・米軍基地・観光〜」だ)。そこを踏まえなければ、過去から受け取った平和を、本当の意味での「平和」として未来に繋いでいけるとは到底思えない。
1970年の時点で「全てを掬い取ることなど不可能である」ということ前提としつつ、それでも本作や本作の中で生きる人々、そして闘いを続けて来た先人達に対して、今の視点でどういった指摘が可能なのか、そしてそれを指摘する言葉(または権利)をその先の平和を生きているだけの自分が有しているのか、何を受け取り先へ繋ぐのか、そういったことも考えてしまう非常に強烈な映画体験だった。
(以下、ネタバレ有り)
とにかく脚本がよく出来ている。先述した「地理の圧縮」と「時間軸の整理」に加え、登場人物の背景を繊細に設定することで、戦後沖縄が抱えた(または現在も抱えている)諸問題とその本質的な原因を浮かび上がらせ、最終的にはミクロな視点、マクロな視点、その両方から「沖縄のアイデンティティ獲得と主体形成を巡る物語」が重層的に展開される作りになっている。
まず、本作第一部で起こる出来事が現実とどのようにリンクしてるのか、地理的・時間的にどのように圧縮・整理され、そこにどのような目的があるのか、それが映画にどのような効果をもたらしているのかを確認する。
映画は主人公の三郎とその両親が平川地区を経由し“石屋”に向かう場面から始まる。
ファーストカット、さとうきび畑の中に置かれたカメラは右へとパンし、一本道を歩く三郎達を捉える。舗装されていない荒れた道、左右に生い茂る背の高いサトウキビ、体力を奪う険しい暑さと鋭い日差し。過酷な状況下、重い荷物を載せた台車を押して移動を続ける彼らは、戦後ひたすら重荷を背負わされ歩き続けて来た沖縄の具体化でもある。
歩き続ける三郎達。すると、どこからか半鐘の音と喧騒が聞こえる。音の先に向かう三郎。そこには土地使用要請(土地強奪のための視察と通達)のために訪れた米軍人とそれを取り囲む平川村の村民達がいた。理不尽な土地の接収に対し抗議の声を上げる村民達だが、その中心にいた男(古堅)の声によって徐々に冷静さを取り戻していく。
本作の第一部である「一坪たりともわたすまい」は、主に伊江島の「土地闘争」をモデルにしている。
終戦直後、苛烈な地上戦と空爆により焦土化した沖縄の土地を「ハーグ陸戦規則(第五十二条)」を拡大解釈することで一方的に奪い続けていた米国。しかし、1952年のサンフランシスコ講和条約発効により、それを根拠とした土地の使用が困難となってしまう。そこで米国側は「契約権(52年公布)」による土地の賃借契約という戦略に打って出る。新たな法的根拠をもとに使用権回復と接収拡大を目論む米国だが、20年という長期契約にも関わらず極度に低額な軍用地料しかもらえない不公平な契約に土地を開け渡す県民はほとんどおらず、これは失敗に終わる。
次に米国がとった行動は「土地収用令(53年公布)」による“法的根拠を持った土地の強奪”だった。収用の告知後30日以内に土地を譲渡するか否かを判断させ、合意がなければ強制的に土地を収用できるこの布令によって米国は沖縄における軍用地課題を「合法的」に克服してみせる。
当時、伊江島で土地の収容告知を受けた人たちの多くは農民だった。農家が土地を受け渡すことは「死」を意味する(実際、土地の強制接収後、伊江島真謝地区では栄養失調者が増加し死者も出ている)。当然、多くの人たちが抵抗した。しかし1953年3月11日、必死の抵抗虚しく、島民は米軍の「銃剣とブルドーザー」によって、土地、畑、家、墓、そこにあった文化、それら全てを根こそぎ奪われてしまう。それから2年後、全てを奪われた島民たちによる沖縄本島縦断の「乞食行進(行脚や口説による非暴力の抗議活動)」が始まる。全県民に「共同体としての自覚を訴える」この行進は、後の一大事件である「島ぐるみ闘争」に繋がる命をかけた行進になっていく。
かなり簡略化したが、これが本作第一部のモデルになった「伊江島土地闘争」に至るまでの流れになる。これを踏まえた上で本作の流れを確認する。
平川村の村民達と米軍の間に立ち、「平川村土地を守る会」で決めた約束を守ることを訴えかける古堅は、行動方針として「短気を起こさないこと」「手を肩より上には上げないこと」「必ず座って話をすること」「挨拶をすること」などの実践を呼びかける。
この「平川村土地を守る会」はおそらく(というかほぼ間違いなく)「伊江島土地を守る会」を元にしている。実際の「伊江島土地を守る会」自体は劇中より後の1961年に結成されているため、ここでは先述した「時間軸の整理」が行われている。また、劇中で古堅が呼びかけた行動方針は「陳情規定」という実際に定められ、実践されていたものである。以下はその内容になる。
一、反米的にならないこと
一、怒ったり悪口をいわないこと
一、必要なこと以外はみだりに米軍にしゃべらないこと。正しい行動をとること。ウソ偽りは絶対語らないこと
一、会談の時は必ず坐ること。
一、集合し、米軍に応対する時は、モッコ、鎌、棒切れその他を手に持たないこと。
一、耳より上に手を上げないこと。(米軍はわれわれが手を上げると暴力をふるったといって写真をとる。)
一、大きな声を出さず、静かに話す。
一、人道、道徳、宗教の精神と態度で折衝し、布令・布告など誤った法規にとらわれす、通りを通して訴えること。
一、軍を恐れてはならない。
一、人間性においては、生産者であるわれわれ農民の方が軍人に勝っている自覚を堅持し、破壊者である軍人を教え導く心構えが大切であること。
一、このお願いを通すための規定を最後まで守ること。
以上が、土地を接収されることになった伊江島真謝・西崎地区の全地主の署名押印をもって1954年に実際に発行された「陳情規定」の内容だ。非暴力抵抗を徹底するこの陳情をもとにした行動は「おとなしすぎる」と批判されることもあった。会の主要人物の一人である阿波根昌鴻(おそらく劇中の古堅のモデルとなった人物)は「かならずしもすぐれた闘いとは思わない。だが、支援団体も、新聞記者も、見る人も聞く人もいないとき、この離れた小島の伊江島で殺されたらおしまいだ。これ以外の方法はない」と語っており、この陳情の性質それ自体が、当時米軍に抵抗することがいかに命懸けであったかの証拠となっている。
場面は変わって夜の浜辺。米軍作業員としての採用に断られ、腹いせの「戦果あげ」の後、夜のもあしびー(野遊び)に興じる三郎と朋子(今作のヒロイン)、弟分の清、そして若者達。
モノクロの世界で白く燃える炎、それによる陰影、歌と踊り、酒と笑い声。当時を生きる若者達の束の間を刹那的に捉え、その生命力をフィルムに焼き付けた非常に力強く美しいシーン。ここで歌われている「海のチンボーラー」という歌は、沖縄本島にある遊郭を茶化した県民なら誰もが知っているような民謡だが、実はこれ自体は替え歌であり、元は「前海スィンボーラー」という伊江島で歌われていたものだ。
悲しい疑心暗鬼によるいざこざの末、もあしびーを離れ別の浜で寝ていた三郎と清は重機のキャタピラーの音で目を覚ます。叫び声と銃声、重機の可動音。音の先にある平川村へ向かう二人。そこでは「銃剣とブルドーザー」による土地の強制接収が繰り広げられていた。抵抗虚しく、生活、文化、過去と未来、その全てを奪われ、軍事演習基地へ回収されてしまった村民達はタスキを掛け口説とともに「行進」を始めることになる。命懸けの行進は止まることなく沖縄を縦断していく。
以上のように本作の第一部は「伊江島土地闘争」の流れをなぞり、また何らかの形で伊江島とリンクするように展開していくことが確認できる。ただ、本作が伊江島という土地で進行している物語かというと必ずしもそうではない(この部分が「地理的な圧縮」が行われている部分)。
例えば三郎と清が軍作業員を基地へと申請しに行くシーン。シナリオ上でこの基地は「中原キャンプ・ゲート前」と書かれている。この中原とは現在の普天間基地の中にある地区のことであり、主題の現場となった伊江島とは離れた場所にある。
その後、断られた二人が戦果あげをするシーン。二人が歩く後ろに「HANSEN GATE 1」の文字が見える。これは本島中東部の金武町にある米軍基地の名前であり、その後の追いかけっこが繰り広げられる町(路地には伊江島との連携を訴える張り紙が至る所に貼られている)はおそらく金武町内の新開地だ思われる(ちなみに、この金武町ではハンセン基地軍用地料を巡る「金武杣山訴訟」と呼ばれる女性差別を告発する裁判が行われていた。また新開地に関しては、当時の資料や村会議員の辺野古視察などから、米兵による性暴力を町内に広げず一定地区に封じ込める狙いをもとに作られたのではないかという考察が桐山節子によってなされている。両者とも非常に植民地主義と家父長制的な色が濃く、本作のテーマとも共通するものがあるが勉強不足なので今回は割愛する)。
このように、劇中の“地理的な整合性”は本作では優先されておらず、限りなく圧縮・抽象化されている。また「土地を守る会」の結成年でも確認したが時間軸も整理されている。そしてこれらは「映画」という芸術形式の本作に対し効果的に機能している。
例えば、会の結成を早めた時間軸の整理についてだが、「平川土地を守る会」という目的と進行方向がはっきりとしている強い組織名は、そのまま映画全体の“矢印”として機能する。もちろん史実通りに会の結成を「乞食行進(1955)」以降の1961年に持ってきても問題はない。しかし各地で散発的に起こる悲劇の数々を羅列するだけのストーリーテリングは映画に混乱を与え、観客の集中力を奪ってしまう場合がある。
「平川土地を守る会(=伊江島土地を守る会)」の結成を史実より早め、物語の中心に据えたことで、「この映画がどこに向かっているのか」「何の話をしているのか」または「観客がどこに集中すればいいのか」という部分に対しての明確な“目印”ができる。このように時間軸を整理することで、本作は映画と観客が混乱するのを防ぐことに成功している。
地理の圧縮は分散する視点の統一につながり、物語をよりタイトにし、そのテーマをより明確にしてみせる。この手法により観客は県内各地に分散していた差別的暴力の数々を主人公一人の視点で追体験することになり、差別される側の苦しみと怒り、そしてこの島が持つ問題の本質をより明確に捉えることが可能になる。
地理と時間の「編集」は映画制作における基本作業だ。本作の第一部は沖縄の1950〜60年代前半を劇映画化することで、沖縄史で呼ばれるところの「暗黒時代」の一端と、その問題の本質を描こうとしている。
ちなみに、史実として、実際の沖縄はこの映画よりさらに悲惨な状況へ置かれていた。「プライス勧告」の裏切りとそれによる絶望、県民同士を内側から分断させるオフリミッツの宣言(セリフでの言及あり)、米軍兵士による暴力事件(特に有名なのが1955年の6歳児幼女暴行殺害事件だ)そういったディティールを省いているという意味では、本作は沖縄県の反基地・反戦運動、民主主義に積極的な県民性をよく思わない人達にとってはある程度口当たりのよい安心できる作品になっているとも言える(それらを描いたからといって本作がよくなるとも思わないし、そもそもそういう人たちが本作を観るとはとても思えないが)。
第二部「怒りの島」は、1968年に起こった全軍労(基地内労働組合の総称)初の24時間ストである「10割年休闘争」に至るまでの道のりを物語の主軸にし、「戦略的政治政策により米国支配がある程度安定してしまった沖縄での抵抗の日々」を描こうとしている。
少し注意が必要なのは、この第二部が第一部に比べて“作り手の願望”や“物語の単純化”がより顕著になっており、結果として「こうであって欲しい戦後沖縄の民主主義」が画面上で展開してしまっていることだ。特にクライマックスはそこで被さるナレーションと感傷的な音楽も相まって、それまで語られてきた一筋縄ではいかないはずの戦後沖縄の怒りが、全て「反基地」や「平和主義」に回収されてしまっているように感じる。
基地内外の労働者の戦いの日々を中心に話が進むこの第二部だが、彼らの怒りや熱狂が実際には何に基づいていたのか、何によって鎮静化されていったのかについては、本作から受け取ることのできるカタルシスやメッセージとは少し距離を置き、冷静に考える必要がある。背景にある1950年代後半の国際自由労連を加えた沖縄統治方式の一大転換とその成果、また復帰後の彼らの運動がどのように変化していったかを踏まえなければ、この時代の沖縄が作り手によって理想化されるだけになってしまう。
第二部は第一部に比べて群像劇色が強く、どこに力点を置き観賞すべきか迷ってしまう作劇だが、作り手の試みはあくまでも「権力に翻弄される労働者達の民主主義的な労働闘争と本土復帰闘争を、反基地・反戦を中心にした平和主義に結びつけ、アイデンティティを巡る物語に仕立て上げること」だ(それはある意味で入門的沖縄戦後史が行なってきた単純化でもあるわけだが)。劇中で起こる様々な要素は一旦置き、当時の沖縄の「労働」という局面で何が起こっていたのかを確認しながらこの第二部を観ていく(古波藏契の「ポスト島ぐるみの沖縄戦後史」が資料として非常に参考になった)。
冒頭、県内の高校でサッカーネット一式がアメリカ軍から寄贈されたことを祝うシーン。校庭に整列する三郎達の次の世代達。第二部の主要人物である山城朝憲の紹介で壇上に上がる米兵中将。見下ろす側と見上げる側、支配する側と支配される側が上下の構図として視覚化される非常に映画的で素晴らしいシーン。作り手はこの構図を冒頭に持ってくることで、これから展開される第二部のテーマを簡潔に伝えてみせる。
第一部からの十年後、三郎は当時年齢を理由に採用を断られた米軍基地労働者として、土地を奪われた平川村の人たちと共に米軍基地内の兵器工場で働いていた。
工場内、スムーズな移動ショットと簡潔なカット割りで人の手を渡っていく兵器、それと並行するように人から人へと密かに手渡されていく労働組合の案内。兵器とチラシを同一ショットに収めることで、暴力的な植民地主義と非暴力を貫く民主主義のせめぎ合いを映画的表現する素晴らしいシーンになっている。
暑さと違法な長時間労働で疲労困憊の労働者達。そんな地獄のような現場で組合への参加を積極的に促している知念という名の男。しかし、三郎を含めた労働者の一部はそんな知念に渋い顔で対応する。平川村で挫折や、極限の疲労状態、基地管理者の監視の目に晒されていた三郎たちは権利のために声を上げることに限界を感じており、抑圧への抵抗に諦めの姿勢をみせていた。
そんなある日、疲労により爆弾の取り扱いを誤ってしまった三郎の父とそれを庇い労働環境に異議を唱えた二人の労働者がパスポートを剥奪され解雇されてしまう。
戦後、強権的に県民の土地を接収し、財産も人権も強奪し続けた米国は、「島ぐるみ闘争(1956)」という“行き止まり”に到着してしまう(第一部の行進の後の出来事)。プライス勧告において沖縄県民を「好戦的民族主義運動が存在しない(つまりゴリ押しできる)」と評していた米国は、この島ぐるみで起きた土地を守るための「総攻撃」に驚きを隠せず、軍事優先主義に根ざした統治方法には限界があると感じるようになっていった。ここから米国は沖縄の統治法を軍事圧力的なものから、経済主義的なものに転換していく。
軍事主義的なものから経済主義的なものへと姿を変えていった沖縄の統治方式。そこで大きな役割を担ったのが国際自由労連だ。強権的な沖縄統治体制により県民のむき出しの怒りを買った米国民政府(米国政府の沖縄行政機構)は、国際自由労連の介入という不本意を受け入れ、沖縄の労働環境改善と経済発展を促すことで県民からの反米感情を抑える策に出る。また、1950年より存在していた「国民指導員制度」という新米エリートを育成するための渡米プログラムにも国際自由労連の介入以降、労組代表が選ばれることが増えていくことになる。米国民政府下において労働組合も労働運動も弾圧の対象となり、悪化の一途を辿っていた沖縄の労働環境は、国際自由労連の介入により急速に改善していく。この“労働者を味方につける統治方式“は、故郷や人としての尊厳を奪われた怒りから来ていた「反基地」「反米」の感情を、より経済的要求を根源とするものに少しづつスライドさせる効果を果たしていった(県民の怒りの捌け口に資本主義を利用したといえる)。
ただ、基地内の労働環境に関しては必ずしも改善したとは言い難かった。国際自由労連が介入するよりさらに前、労働三法の影響で基地内の労働者が人権意識を持つことを恐れた米国民政府は、その影響から労働者達を引き離すため布令116号(53年)を発布する(劇中のセリフにも出てくる)。基地内労働者を労働三法適用外とするこの布令。これにより沖縄の軍労働者達は組合活動を規制され、最悪の労働環境下で抗議の声も上げることも、交渉の場を持つことも難しく、馬車馬のように働かされていた(この布令は国際自由労連の介入後も存続し、1968年まで影響力を持ち続けた)。違反者にはパスポートの剥奪や解雇が待ち受けており、土地を奪われ基地で働くしか経済的自立を達成できない農村出身の軍労働者達は、様々な不条理も受け入れるしかなかった。
パスポートを取り返したい三郎は基地管理者と話し合いの場を設けるが、そこで見返りとして「スパイ」になり全軍労を内部から撹乱することを持ちかけられてしまう。それを断った三郎は怒りや悔しさの中、夜の街を彷徨い、改めて米国民政府の圧政に闘志を燃やすことになる。そんな時、知念から「10割休暇闘争が始まる」との知らせを受ける。闘争に向けて士気を高めていく三郎をはじめとする軍労働者。しかし、三郎の軍労働者への強い影響力を知る基地管理者は、彼の意中の人である朋子の逮捕をチラつかせ、闘争を内部から分裂させるよう彼に強い揺さぶりをかける。
この「10割休暇闘争」とは、1968年4月に起こった「10割年休闘争」がモデルになっている。基地内での労働環境が最悪の状況であったことは先述したが、それに加え1960年代後半は、本土復帰の機運が高まったこともあり、軍労働者の大量解雇が断続的に発生していた。この理不尽な労働環境と大量解雇に対抗するために全軍労がとった行動が「10割年休闘争」だった。布令116号が発布されて以降、ストライキが禁止されていた全軍労は「年休」という言葉を使うことで、布令に抵触することを回避しようとした。全員参加という意味で使われた「10割」という言葉。総勢2万人が参加したとされるこの大規模な闘争は、全軍労初の24時間ストライキだった。
米国民政府の揺さぶりに敗れ、全てを諦めた三郎は平川村に戻りキビ畑で農業を手伝っていた。そんな彼を再び闘争の場に押し戻そうとするかつての仲間達。組合の先頭に立っていた知念が逮捕されたことを知り、更には平川の組合小屋が焼き払われるのを目の前で目撃した三郎。小屋を焼く米兵に抵抗し逮捕されてしまう彼だが、怒りと共に再び立ち上がることを決意する。
基地内、24時間ストを警戒していた米国民政府は先手を打っていた。各組合同士の連絡手段を断ち、その上で強制解雇をちらつかせる彼らに組合は揺らぎ始める。そこに現れた三郎。釈放寸前、変わり果てた知念の姿を見た三郎は彼の言葉と共に疑心暗鬼に陥る組合員達を鼓舞する。決意を固めた全軍労はついに24時間ストに突入することになる。
以上のように第二部も戦後沖縄で実際に起きた出来事や当時の労働者達の状況がモデルとなっているのが確認できる。故郷を奪い尽くした相手に奉仕することでのみ約束される生活。屈辱の日々の中で労働運動という政治的抵抗手段を手にする三郎達。「自分たちにとって何が不当なのか」「自分たちが何に憤りを感じるのか」「自分たちが何を求めているのか」、そこにある理不尽な状況と、それを起因とする負の感情を自分たちの言葉と行動で訴える労働運動という抵抗手段は、一度失った自己を再び“言語化”し“規定”する手段でもあったはずだ。登場人物達が政治的抵抗の果てに「自分たちが何者であるか」を主体的に選択していくプロセスこそ、この第二部のテーマだと言える。
第一部で土地を奪われた農民達が、その土地を奪回する闘争に自己を見出し、第二部では権利を奪われた労働者達がそれを獲得する闘争に自己を見出していく。これらの闘争は“共同体”を通して当時の沖縄に実際に起こった時代のうねりだ。作り手は戦後沖縄の“共同体を通した闘争”にマクロな視点からの「アイデンティティを巡る物語」を読み取り、本作を描いている。
当時の苦しみの後に生まれた県民としては、画面上で展開される差別の連続に悔しさや怒りを感じずにはいられない。失った土地やそこに根付いた生活、歴史、文化、その全て結局は奪い返せなかったという史実は今も現実の問題として存在している。だからこそ、劇中後半のストが達成された瞬間の歓喜や、言論で立ち向かう人たちの姿に感動し勇気づけられもする。しかし、先述したように、本作の第二部が戦後沖縄の歪さを単純化し“理想化”しているのも事実であり、その部分も指摘しておかなければフェアとは言えない。
本作の第二部は全軍労のストに向けた労働闘争を中心に話が展開していくが、終盤はそれに重ねるように沖縄の「本土復帰」に向けた時代の変化も描かれている。本作がアイデンティティ獲得をテーマの中心に据えてることを考えれば、「本土復帰」という当時の県民のアイデンティティ獲得の集大成を物語の終盤に用意したのは非常に正しい選択だと言える。そして、それは歴史的にも正統性がある。なぜなら「本土復帰」に向けて最も重要な存在だったのが全軍労を含め県内各地に存在した「労働組合」だったからだ。
では、なぜ本作第二部の描かれ方に“理想化”を感じるのか。それは「本土復帰」に対する全軍労の立場や、その闘争の性質に史実と若干のズレを感じるからだ。本作の作り手達は、全軍労を中心とした労働組合の闘争と「本土復帰」の闘争に「反基地」「平和主義」の性質をかなり強く見出している(その証拠にナレーションでわざわざベトナム行きの爆撃機を停止させたと強調する。まるでこの闘争の果て勝ち取った平和の一つであるかのように)。確かに「本土復帰」のスローガンは「即時・無条件・全面返還」であり、その闘争の中には「戦争反対」の文字も掲げられていた。その意味においては本作後半の闘争の描かれ方は間違っていない。が、実際にはそんな単純な話ではない。もし仮に、当時の闘争が純粋な「反基地」「平和主義」の旗のもとに繰り広げられていたならば、「本土復帰」達成後の沖縄の現状に説明がつかなくなってしまう。何故なら、復帰を境に全面返還の運動は急速にその勢いを失い、広大な米軍基地は沖縄の土地に今なお存在し続けているからだ。
沖縄の「反基地・反米」運動は時代と共にその性質を変化させてきた。たとえ同じ県民総動員の闘争といえど、本作第一部の先にある「島ぐるみ闘争」と、第二部の先にある「本土復帰闘争」を同じ性質の「反基地・反米」として語るには若干無理がある。しかし、本作はこの二つの闘争を主人公である三郎の人間臭くも最終的には労働者代表として振る舞う英雄的なキャラクター性を利用し同じように扱ってしまっている。
ここで重要になるのが、先述した“当時の沖縄の「労働」の局面で何が起こっていたか”だ。第二部における沖縄の反基地・反米の姿勢が、国際自由労連介入や米国民政府の統治方式の転換、国民指導員制度による新米エリート育成によって穏健化され、その性質を経済要求的なものに少しづつ変化させられてきたのはすでに確認した通りだが、それに加えて、復帰が現実味を帯びてきた60年代後半は基地労働者の強制大量解雇が断続的に発生していた(本作の第二部はそのゴタゴタが「10割年休闘争」に発展するまでの物語だ)。この時期、全軍労は大規模な闘争を幾度か仕掛けるが、その原動力は「不当な労働環境を訴える」ことや「不当な解雇を訴える」という“経済的危機”に起因するものでもあり、必ずしも「反基地」「反戦」だけがテーマではなかった。そしてこれは全軍労だけではなく、当時の沖縄県全体に対しても指摘が可能な事実だ。当時、復帰運動の際に使用された「本土なみ」や「差別なき復帰」というスローガンは、不平等な基地負担や、命や尊厳を軽んじらている現状を不問にされる人種的差別(あえてこの言葉を使うが)に対してのみ発せられた訳ではなく、本土との賃金格差解消や経済成長率の改善など、経済的差別に対しても発せられていた。事実、1968年に行われた県民に対するヒアリングでは、80%近くの県民が復帰支持を表明しながらも、基地全面返還については「賛成34%、反対32%、わからない34%」という結果も確認されている(実際、オフリミッツ発令の後、基地からの利益に依存する県民側が反基地デモを行おうとした学生達を集団で取り囲んだという記録もある)。
上記の内容だけでも、当時の怒りや熱狂を「反基地」「反戦」や「平和主義」のみから読み解くのは難しくなるはずだ。しかし、本作の作り手は経済的危機からも来ていた闘争の原動力を、クライマックスの熱狂に乗じて、純粋な「反基地」「反戦」に塗り直してしまう。少なくとも本土復帰のエネルギーは資本主義的な欲求に突き動かされていた側面があり、当時の熱狂に身を投じた人たちの中にも少なくない割合で基地共存を望んでいた者たちが居たことを見逃してはいけない(その是非が問いたいわけではなく、事実として「複雑」だったということ)。本作の全軍労も三郎も、その他の組合組織も、作り手の願望により少しヒロイックに描かれ過ぎているような気がする(もしくは作り手が望むヒーロー像に作り変えられている気がする)。
第一部と第二部が当時の社会を劇映画化することでマクロな視点からの「沖縄のアイデンティティ獲得と主体形成を巡る物語」を展開させたように、本作は登場人物の的確な背景設定により、ミクロな視点からもそれらの実践が行われている。またそれぞれの登場人物は当時実際にあった出来事や制度に振り回された県民がモデルになっている。各登場人物を確認することそれ自体が、戦後沖縄を読み返すことにもつながる作りとなっている。
例えば、主人公の三郎とヒロインの朋子はそれぞれ、「戦果アギヤー」「廃品回収業」で生計を立てるが、どちらも当時の沖縄で実際に行われていた「職業」だ。米国に土地を奪われ生計を立てる手段を失った人たちが、彼らの物資や廃品で生きるという不健全な依存のサイクルを端的に表すこれらの職業は、その存在自体が当時の沖縄の過酷な状況の証明となる。
存在感は薄いが、三郎の弟分である清も「琉球政府計画移民」という実際にあった政策に振り回された人たちがモデルになっている。土地の接収や人口増加により発生した人口過密、そこから来る失業率の増加など、様々な社会問題を打破することを狙って実施されたこの移民計画だが、ボリビアを中心に南米各地へ渡った当時の県民は、移住先で非常に厳しい経験をすることになる。感染症や水害、移住を促進した米政府からの支援が途絶えたことなどにより、移住定着率は10%以下だったとされている。劇中の清の様に、海の向こうで全てを失い故郷に戻ってきた県民は数多くいた。
“女性”教師の桃原は劇中最もロジカルな「本土復帰」を唱える人物だが、当時の教職員会は、多くの組合の中でも復帰運動の前線を担ったことで知られている。彼女の存在自体が、当時の沖縄の教育という場で起こった政治的せめぎ合いと、その中で子供たちの未来のために戦った教職員会の具体化でもある。
アメリカ留学帰りの山城朝憲は、「国民指導員制度」で海を渡った新米エリート達がモデルになっている。金の匂いを真っ先に嗅ぎ取るハイエナ(ハイエナさんに失礼なのでゴミクズでも可)を父に持ち、理想と現実の間で揺れ動く彼は、物語の終盤まで「自分が何者なのか」を自問し続ける。その姿は、海を渡り自由の国の精神性にアイデンティティを見出したにも関わらず、持ち帰ったそれと故郷の現状に整合性をとれず、日和見的にどっちつかずな態度で振る舞うしかなかった実際の指導員達の姿と強く重なる(当時の指導員の中には、アメリカが語る理想が沖縄で実現できていないことの異議申し立てをする大城つるのような勇気のある人もいれば、米国に対して批判的な言動を行った同じ指導員を密告するという恥も外聞もない卑怯丸出しなヤツもいたと言う、しかもこいつ立法院議員な)。
故郷の現状を憂いながらも、曖昧な立場と曖昧な言論、曖昧な行動で、未成年の教え子相手にも親譲りの卑怯さを発揮してしまう朝憲は“人間の内面の複雑さ”や“世界の多面性”を体現する非常に素晴らしいキャラクターだ(その意味では劇中最も泥臭い人間と言える)。また彼の揺れ動く内面それ自体が、「理想(平和)と現実(経済)」の間で揺れるしかなかった当時の沖縄の世論の具体化と読むこともできる(とはいえ、その現実も基地安定のために権力側が都合よく作り出した物であることは指摘しておきたいが)。
「アイデンティティを巡る物語」である本作のテーマを最も体現している登場人物がヒロイン朋子の弟である亘だ。アフリカンアメリカンの米兵と性産業で生計を立てる母との間に生まれた彼には常に差別の視線が付き纏う。敵意剥き出しの差別、悪意のない差別、そのどちらもが彼を苦しめる。米国、日本、沖縄、そのすべてから異端として扱われる彼は、周りの大人が与えてくれない“自分の居場所(または自分という存在)”を自分で掴み取らなければならなくなる。
亘の人生は朝憲の物語と対になるように描かれている。有力者の息子として何不自由なく沖縄県民と認めてもらえる朝憲と、そうはならない亘。国民指導員制度を利用し米国からも沖縄からも期待をしてもらえる朝憲と、その両方から異端者扱いされる亘。社会から安全な居場所を与えてもらいながらも自身のアイデンティティに確信が持てない朝憲と、社会から周縁に追いやられてもそれでも高らかに「ウチナンチュ」を宣言する亘。他者の死によって初めて自己を確立する朝憲と、死ぬことで初めて他者から存在を認めてもらえる亘。教師と生徒という立場で再会し、自己を求めてもがく彼らの物語は、間違いなくこの映画の核だといえる。(だからこそ映画を観ている途中はひたすら朝憲が情けなくて呆れてしまうのだが)。
亘の悲しすぎる結末は、泉崎という場所で実際に起こった轢殺事件がモデルになっている(その証拠に劇中で亘が事故に合うのも泉崎交差点になっている)。当時中学生だった国場秀夫さんが米兵の運転するトラクターに轢き殺されたこの事件は、劇中同様、最低の裁判のもとで最低の結末を迎える。この事件は、日米地位協定の理不尽さを知らしめる事件として象徴的な事件になっている。
日米地位協定の問題点と戦後沖縄の社会の不安定さ、その両方を十数年という短い人生の中で一身に体現する亘は、本作において作り手から「最も背負わされた人物」だと言える。
登場人物たちが、それぞれに背負った人生の中でもがき、苦しみ、泣き笑いする姿を捉えることで本作は戦後沖縄という一つの“時代”をミクロな視点から描くことに成功している。
冒頭で述べた「今の視点で本作(または当時の沖縄)をどのように語れるか」「どのように語り繋いでいくべきなのか」という部分について、目の前の「平和」に何の疑問も持たないで済むような、“普通という贅沢”を与えられてきた自分としては非常に躊躇してしまうが、それでも本作が沖縄の加害者性を「漂白」してしまっていることは指摘しなければならない。
例えば、本土復帰運動に通底した強烈なナショナリズムがもたらした他民族への差別意識だ。「沖縄人、朝鮮人お断り」という張り紙が本土の貸家に貼られていたという話にもあるように、戦後の沖縄県民は朝鮮に出自を持つ人々同様、差別の対象とみなされた。しかし、そんな彼らの中にも朝鮮人を見下す意識があり、「彼らとは区別されたい」という差別的意識が本土復帰の原動力の一部になっていたのも事実だ。実際、戦後の語りの中や、国や県による第二次大戦の被害者調査の中でも、朝鮮人被害者に焦点が当たることはほとんどなく、その存在は不可視化されていった。
同様の不可視化はジェンダーの局面からも発生した現象だ。詳しくは先述した玉城福子の「沖縄とセクシュアリティの社会学」を是非読んで頂きたいのだが、沖縄戦後史が雄弁に語る“男達の英雄譚”の裏で、どれだけ多くの女性達の存在が無かったことにされたか、彼女達の主体性や、英雄達から受けた数多の性差別が無かったことにされたか、米兵相手の性産業に生きるしか無かった女性達が同じ県民からどのような扱いを受けていたか、という部分に関して今を生きる県民(特に自分を含めて特権的な性に位置する人間)はもう少し意識的であるべきだ。
本作も、米兵相手の性産業に身を置くことで地獄を生き延びた、さわ子という名の女性が出てくるが、本作の彼女に対する視線は、一見するとフェアなように見えて、実際は非常に際どいバランスの上に成り立っている。劇中の彼女は常に他者から「批評」され続ける。息子である亘からの恨みの言葉、娘の朋子からの軽蔑の眼差し、世間や政策からの嘲笑と裏切り。様々な言葉と態度を尽くして彼女を批評し侮蔑する彼らだが、そんな彼らの言葉が本作から批評し返されることはない。それどころか、本作は彼女と朋子を対比的に描くことで、「米兵相手に性を売ることで生活費を稼いだ女」と「廃品回収で生活費を稼いだ自立した“強い”女」という対立構図を作り出してしまっている。確かに本作は彼女に理解を示すかのような“演出の余白”を設けている。しかし、悔しさと悲しさの果てに溢れた彼女の叫びと涙は、三郎と亘の間で飛び交う怒号にかき消され、朋子の憐れむような「優しい」視線でうやむやにされてしまう。結局、“戦後沖縄”という圧倒的男性優位社会の中、一人の女性が必死の思いで獲得した主体性と苦渋の選択の連続は、特権的な立場にいる男性映画監督から、映画表現という特権的な手法で一方的に批評されてしまう(ただ、それでも脚本段階より確実に彼女の描かれ方は複雑で多面的にはなっているし、そもそもそこを描くのが本作の目的ではないともいえる)。
もっとも顕著な「漂白」が行われているのがラストのナレーションだ。先述したが、本作はベトナム行きの爆撃機がストにより機能不全に陥ったことを「沖縄県民が勝ち取った平和」のように表現している。当たり前だがそんなことは絶対にない。確かに、戦後沖縄ではベトナム戦争に対する反対のデモがいくつも起こった。しかし、それでも沖縄は「ベトナム特需」という甘い汁を啜っていた側だ。この事実からは絶対に逃れられない。本作も一度は主人公の口からベトナム戦への言及を行っているが、それでもその加害性に向き合うことなく、最終的にはベトナムの状況を憂いてるような姿勢を見せてしまっている。これは完全に欺瞞であり本作最大の欠点の一つだ。ベトナムにとって沖縄が「自分たちを殺す為の武器を作り、供給し、それで利益を得ていた“悪魔の島”だったこと」は、沖縄が向き合い続けなければならない負の歴史だ。
正直、「こうするしかなかった」過去の選択の連続を、与えられた豊かさに浸かりながら今の視点で批評することに、ある種の傲慢さがあることは否定できない。しかし、差別をする側がさらなる差別を行うという“差別の再生産”が繰り返される限りは、例えそれが感謝し尊ぶべき人たちの行いであっても批判的に指摘しなければならない(そして、その批判の矛先は常に自分にも向けなければならない)。今を生きる自分たちのために過去から繋がれた営みの連続が、誰かの犠牲の上に成り立っていたなら、例えそれが感謝し尊ぶべき人たちの行いであっても批判的に指摘しなければならない(当然、その批判の矛先も常に自分にも向けなければならない)。
あの日から今に至るまで、確かに沖縄は多くの被害を被った。逃れられない負の歴史も、圧倒的な力を持つ権力者達が、県民の命を人質にして押し付けたものだともいえる。それでも「漂白」の欲望には常に抗わなければならない。そうしなければ、過去から受け取った平和を、真の意味で未来に繋ぐことはできない。
次に本作のような戦後の沖縄を描く映画が作られるならば、今度は沖縄戦後史から周縁に追いやられ、不可視化された人たちの視点から語られるべきだ。沖縄から飛び立った戦闘機で殺された人たちの視点も描くべきだ。千鳥足じゃないさわ子がこの島を歩き、飛び立った戦闘機の先にある焦土を描いた時、本作にも劣らない沖縄映画の新たな傑作が誕生する気がする。
思い入れの強い土地を描いた映画であるため非常に長くなってしまった。受けた感動や作り手の理想的な沖縄像に水を差すような批判的内容も書いてしまったが、それでも間違いなくオールタイムベスト級の映画体験だった。この映画のように、あの地獄を生き延びた全ての人たち、もしくは今も沖縄で笑ったり、泣いたり、怒ったり、サーターアンダギーで咽せて焦ったり、白い息が出てテンション上がったり、台風でユニオンの状況を確認したり、二段階右折に迷ったり、お墓の前でブルーシートを敷いていたり、仕事に行ったり、家事をしたり、子供を寝かしつけたり、夫婦でゆっくりしたり、一人でまったりしながら生きている全ての人たち、本当にありがとうございます。傑作。
※参考資料の「ポスト島ぐるみの沖縄戦後史(著:古波藏契)」と「沖縄とセクシュアリティの社会学〜ポストコロニアル・フェミニズムから問い直す沖縄戦・米軍基地・観光〜(著:玉城福子)」にはとにかく感銘を受けた。本当に勉強になったし、考えさせられもした。近い年代の人たちがこういった研究を読みやすい書物として外に提供してくれるのは素直に尊敬してしまうし、本当にありがたく感じる。沖縄県民には是非読んでほしいと思った。
※ジェンダーに関する「漂白」の部分について、差別する側に属する自分が、被差別側に属する人間の行った研究のタイトルだけを記載し、「詳しくは読んで」で終わらそうとする姿勢は、それ自体が自分の位置性を見誤った非常に不誠実で失礼なものなわけだが、現状この本を読んで受けた衝撃を言語化できる能力が自分にはないので、本当に「詳しくは読んで」くださいって感じっす(ってことを書くこと自体が不誠実な言い訳でしかないんだけども)。
※沖縄史での国際自由労連の評価は二分されている。労働組合の育成や米国民政府からの弾圧の防波堤を果たした国際自由労連だが、彼らの本質はどのような言い回しをしようが「米軍基地を沖縄に定着させるための装置」でしかない(これは揺るがない事実だ)。この捻れをどう評価するかは、各個人が現在の沖縄の有り様をどう評価するかで変わってくる。個人的には、国際自由労連という組織が、自身を民主主義の体現者としながらも暴力で小さな島を横断してしまうアメリカの自己矛盾とそれによるジレンマの視覚化のように思えて興味深かった(もちろん国際自由労連は米国からは独立した国際組織であるが)。何にせよ、軍政を敷き全てを蹂躙できる圧倒的な軍事力を持ちながらも、そのジレンマにある種の自己批評(ここでは国際自由労連の介入)をするアメリカに、玉座のない超大国の歪な底力を感じた。
※本作の「上平川」と「下平川」は実際に沖永良部島にある地名だ。どういった意図があってこの地名を採用したかは不明だが、沖永良部島は琉球の文化が根付いており、戦後アメリカ軍政下に置かれていたという意味では、ゆかりがあるとは言えなくもない。しかし、沖永良部島は琉球よって支配されていた島だ(つまり琉球の加害の歴史の先にある島だ)。植民地支配の暴力性を暴く物語で、沖縄が武力支配していた沖永良部島の地名の一部を採用するのは、正直かなり無神経で欺瞞的な気がしてしまった(単なる思い込みなのかもしれないが、居心地が悪いのは確かだ)。
※本土にある米軍基地のほとんどが国有地だったのと違い、沖縄のそれは8割が元々民間の土地または県の土地だった。沖縄県民の反基地・反戦運動に対するカウンターとしてよく利用されるロジックの一つに「基地があるのは沖縄県だけではない」というものがあるが、上記から見てもわかるように「政治的スタンス」などという次元ではなく、根本的な基地の成り立ちとその性質が違うことは指摘しておきたい。また、本土の基地では「無し」だが、沖縄の基地でなら「有り」となった事が多くあったことも指摘しておく(核兵器の持ち込みとか)
※第一部のタイトルは昆布地区土地闘争の際に作られた歌のタイトルが元ネタとなっている。
※本作は、「沖縄料理」がほとんど出てこないが、この時代は「琉球料理」と「沖縄料理」の間の時期と言える。ポーク入りとそうでない白黒のゴーヤーチャンプルーを見てみたかった気はする。